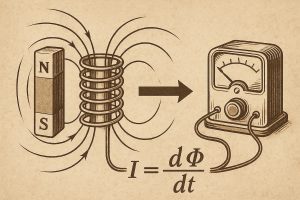【平城京 8月29日発】
朝廷は本日、新たに鋳造された銅銭「和同開珎(わどうかいちん)」を発行すると正式に布告した。国内での本格的な通貨流通を目指した施策で、これまで物々交換や布、稲穂で行われてきた取引の制度化を進める狙いがある。発行に先立ち、武蔵国秩父郡(現在の埼玉県秩父)で和銅と呼ばれる良質な銅が産出されたことが契機となった。
河内鋳銭司によれば、和同開珎は直径約2.4センチの丸銭で中央に穴を開け、表面に「和同開珎」と鋳刻。これまで使用されてきた渡来銭「開元通宝」を参考に、国内の独自貨幣として設計された。貨幣価値は布や稲に換算して定められ、租税納付や市での売買に広く利用される見通しだ。
発行布告の場で元明天皇は、「新たな銭をもって、国を治め、交易を盛んにせよ」と述べ、中央集権体制の強化と経済活性化への期待を示した。朝廷関係者は「国造りの要は租税の整備にあり、貨幣の導入はその第一歩」と強調する。
一方、市井では戸惑いの声も上がっている。平城京の市では、商人の一人が「銅の板きれで米が買えるのか、まだ信用できぬ」と語る一方、若い農民は「布を使わずに取引できるなら楽になるかもしれない」と期待を寄せた。和同開珎を早くも受け入れる商人と、従来の物納を続けたい農村勢との間で、当面は混乱が生じる可能性もある。
朝廷は年内に銅銭の鋳造をさらに拡大し、全国の主要市場へ流通を進める方針だ。
新しい貨幣が定着するか否かは、国政と民意の両面にかかっている。
— RekisyNews 政治・経済面 【708年】