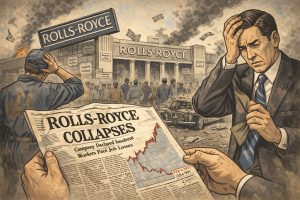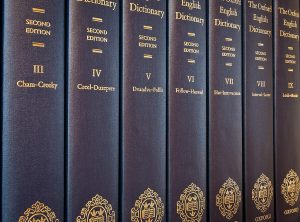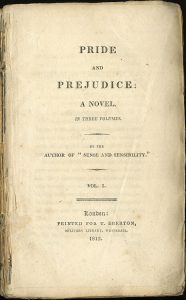【ロンドン 8月20日】
英国放送協会が本日、音声放送に映像信号を重ねる試験番組の送出を開始した。機械式走査による低い走査線の映像は小窓に人影と文字を揺らぎながら映し出し、受像側の改良次第で輪郭は次第に明瞭になりつつある。番組は出演者の顔の拡大、天気の簡易図、タイトル表示など。
最も難しいのは同期の調整で、送出側と受像側の円盤の回転が少しでも狂うと、像はねじれ、人物の顔は鋸歯状に崩れる。照明の熱で機材が膨張し、ピントが流れる事態も起きる。技術者は送受双方の現場を行き来し、明滅の周波数やシャッターの位置合わせをその場で修正した。
それでも、人々の居間に「声」に続いて「姿」も届く時代は近い。教育番組や劇場中継、議会報告、遠隔講義の可能性が開け、緊急時には避難情報を図と文字で示すことができる。受像機の価格低下と感度向上、スタジオの防音と照明設計が課題だが、産業界は参入の構えを見せる。
実験は視聴者の参加も得て進む。郵便で届く評価票には「目が慣れると人物がわかる」「照明を強くすると文字が読みやすい」など具体的な指摘が並ぶ。放送協会は収集した意見を翌日の調整計画に反映し、改良の速度を上げる方針だ。
送信塔の赤い灯が夜更けに瞬き、スタジオではリハーサルが続く。少年が店先の受像機を覗き込み、ぼんやりした人影に手を振った。電波は、耳に続いて目をつなぐ。新しい窓が、テーブルの上に開こうとしている。未来は近い。
— RekisyNews 放送・技術面 【1932年】